こんばんは。
あまりにも寒いので、今夜もあたたかいカフェの思い出をお送りしよう。最近もどうも忙しいし、ちょうど去年の今頃の僕って、何処に出かけただろうか……と写真をぱらぱら見返していると、あったあった。こんなものが。
「星乃珈琲店 スフレ館」
金色のプレートが眩しい。わくわくしていたあの日の記憶が蘇ってくる……。

星乃珈琲店はご存じドトール・日レスホールテディングスが経営するチェーン店なのだが、シックな内装が心地いいわりと大人な空間だ。カフェ研究家を自称すると、マイナーなお店ばかり行く気難しい人だと思われがちだが、こういう気さくなお店も大好き。
といっても、大企業の経営戦略に乗っかって、なんでもかんでも宣伝するような気はさらさらないし、例えば、わゆるインスタ映えばかり狙ったような見た目重視のスイーツ(笑)や、牛丼チェーンよろしく苛烈な価格戦争を目の当たりにすると目の当たりにすると心がぐったりしてしまうのだが……まあ、たまには、大人の苦労や業界の厳しさなどほとんど知らない中学生くらいの異邦人になったつもりで、チェーン店を訪れてみよう。
さておき、「スフレ館」である。
星乃珈琲店は星乃珈琲店でも、ただの星乃珈琲店ではない。「スフレ館」なのである。
この店舗はちょっとレアで、文字通りスフレのメニューが充実している。Souffleとは、フランス語で「炊いた」を意味する、メレンゲを使用した料理のこと。日本ではスフレパンケーキなど、ふわふわ甘々スイーツが有名だが、実は主食にもなる、懐の深い料理だ。
スフレ館は、関東では、今回紹介する下北沢店と、新宿東口店があるのだろうか。もしかしたら今後もっと増えるかもしれないし、増えないかもしれない。「ここはチェーン店だけど、実はここにしかないメニューがあるんだ」なんて云えたら、中高生のデートでは微笑ましい合格点ではないだろうか。知らんけど。
下北沢にあるスフレ館は地下にあって、階段を下りていくと、ダウンライトの落ち着いた雰囲気が広がる。この日は雨で、僕が訪れたのは16:00くらいだっただろうか。中途半端な時間だったにもかかわらず、階段を下りた入り口のところには結構人が並んでいて、人気ぶりが伺えた。
下北沢といえば、ライブハウスや個性的なバー、古着屋さんといった、若者の街という印象があるが、並んでいる人たちはやや年齢層が高めで、こころなし渋めの人が多い気がする。いい歳こいた男で、スフレスフレとはしゃいでいるのは僕くらいなものだ。そんな感じが、またいっそう若い時分を思い起こさせ、勝手に盛り上がる。
この日注文したのは、ビーフシチューのスフレドリア。価格は、確か1000円。普段読まない新聞でもひろげて待っていると、おお、来た来た。

見よ。

生地がしぼんでしまわないか躊躇しながら慎重に、スプーンの先で分厚いスフレ生地を破ると、あつあつとろとろのビーフシチュードリアのおでましである。スフレとビーフシチュードリアをちょこちょこと混ぜながらいただく。
はじめに適温なスフレのふわふわ食感とほどよい塩気がきて、きのこやビーフの滋味と食感が追いかけてくる。何よりの醍醐味は、熱いブラウンソースに包まれたライスの”のど越し”だろう。オムハヤシが大好きな人は、もちろん大好きな味と食感に違いない。しかし、オムハヤシとは全く別物。甘い嘘のような、未知の世界である。もくもくと食べていく。
チェーン店なので、何かにつけて、多少の作り物めいた感じや無関心な感じは否めない。それなのに、どうしてこうも居心地よく感じてしまうのだろうか……。どうして僕らは、こんなおいしいものを、こんなにもお手軽に食べられてしまうのか。企業と消費者の関係。人と人の関係。街とは何なのか。社会とは何なのか。僕とこの店の間には、いまだ茫漠すぎる時間が、どうしようもなく横たわっていた。
でも……
僕をとらえたその不安は、やがてゆるやかに溶けていき、後には、スフレのやわらかなふわふわだけが残っていた。

食後はまったりとブレンドをブラックで。ごちそうさまでした。
.bmp)


















 とろける。
とろける。




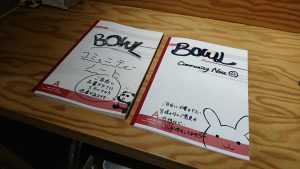 ありがとうございました。またいつかお会いしましょう。
ありがとうございました。またいつかお会いしましょう。












